カテゴリー ~ コンサルティング
遠隔地店舗を経営するためのコツ
皆さん、こんばんは!
株式会社チームのちから
植竹剛です。
もうすぐ日付が変わりそう
ですが、クライアント先との
会議が今しがた終わりました。
やっぱりやる気マンマンの
経営会議は熱気ムンムンです!
それでは本篇に入ります!
今日のブログテーマは
「遠隔地店舗を経営するためのコツ」
これは今日昼間に
スポットコンサルティング
させていただいた社長さんの
切実なお悩みでした。
オーナー所在地と店舗が離れている
ケースでは組織規模が大きくない場合は
オーナーの継続的情熱を現地まで実際に
足を運んで伝え続けなければなりません。
でも、経営者は何かと忙しい。
週に半分(3-4日)なんてとても
行ってられない、というご相談でした。
昨年東京本社⇔沖縄店舗の
コンサルテーションをさせて
いただいたときの合言葉は
「自立型組織をめざす」
でした。
評価、報酬システムはオーナーが決めて
採用、教育システムは店長が決める
評価の原点は信賞必罰
教育の原点は才能発掘
お互いの仕組みに対する考え方を
理解、納得するまで協議する。
地道で骨が折れることもありますが・・・。
でも、はい、コレ王道です。
後はホウレンソウの効率化
店長出勤日は毎回5分の
コミュニケーション【顔が見える媒体を使って】
お互いの表情観察は超重要
うん?なんかおかしいな?と感じたら
最速で三現(現物・現場・現実)主義を実行、
リアルミーティング実施です。
ちょっとした変化を見過ごさず、
すぐにオーナーが動ける体制を
作っておくことが大切です。
どこまで行っても薄氷の上を
歩いているという、
神経を適度に緊張させておく
経営者の覚悟が必要です。
おっと、王道といいつつ
階段を踏み外しそうに
なりました。こりゃイカンです。
そうです。Whyの確認です。
つまり、
Why
なぜここに集まって働いてがんばるのか
→ミッションステートメントづくりが
まずは必要不可欠です。
原点回帰の場所をつくる。
これめっちゃ大事です。
まとめると
①ミッションステートメントづくり
②人事サイクルを回す仕組みづくり
③ホウレンソウをマメにするルールを決める
これが初期に決めることです。
まだまだ考えることはありますけどね^^
さぁて!
明日もバリバリ行きましょうか!
株式会社チームのちから
代表取締役 植竹剛
人を評価するときの尺度とは?
【社員になるかアルバイトのままでいるか】
店舗の困った!にお応えする
店長養成道場の植竹剛です。
昨日のクライアント先での出来事です。
オペレーション(店舗業務)が優秀な男性のアルバイトがいます。店舗の今と数時間先を予測しながら、適切な指示を後輩アルバイトにしていきます。
体も良く動き、自ら率先垂範してくれます。
と、ここまでは高評価なのですが問題は「根っからのネガティブ思考」。
自分はまだまだ。全然今の自分に自信が持てません。なので社員にはなれません。
過小評価の典型です。でも私はこの自己評価も加味して人物評価をします。
店長代理からは「ぜひ社員に」と推薦が上がってきています。ですが、私はこのように返答しました。
『社員になってもっとお客さまのため、他のスタッフのために尽力したいという気持ちを持たせて上げられていない我々の責任なのでまだダメです』
はい、「これも仕組み憎んで人を憎まず」です。
結局はもう3か月間はアルバイトとして雇用契約を巻き直しました。
ここからが組織も個人も頑張り時です。
さて、朝礼に参加してきます^^
女性スタッフが業務中突然泣き出す店舗とは・・・?
皆さまこんにちは!
店舗の「困った」にすべてお応えする
店長養成道場の植竹剛です。
このタイトルは何だ?と思われたことでしょう。
心理学の専門家ではありませんので
断定はできませんが、
「嫌なこと、辛いことを思い出したフラッシュバックの結果」
ではないかと推測しています。
なんと、ある店舗の女性従業員全員が経験している
という実態が明らかになりました。
パワハラという言葉だけでは言い尽くせません。
怒りとともに憤りを感じています。
確かに、年齢も若く社会人経験も豊富ではない
メンバー構成です。
しかし、だからこそ「長い目」で人材を観察するしかありません。
——————————————————————-
たしかに労働生産性や販管費管理においては
「キビキビ」と「精度高く」働いてもらった方が良いです。
しかし教育責任を果たせているのか、という自責の念を
感じていないとこのような結果になりがちです。
ではその感受性をどのように磨けばよいのか。
私は身の回りの5S活動だといつも申し上げます。
5Sとは
整理
整頓
清掃
清潔
躾
のことを指します。
順番もこの通りなのです。
整理とは不要なものを捨てる、という意味です。
整頓とは定位置を決め、その場所に戻す行為です。
清掃は上から下、奥から手前、隅から中央に行います。
清潔は清掃の習慣化と状態維持を指します。
この4点ができて初めて「躾」ができるのです。
躾=身を美しく
やっぱり経営者は「お手本→従業員は自分の鏡」
という結論は今も昔も変わりませんね。
店長養成道場
植竹剛

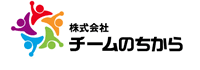

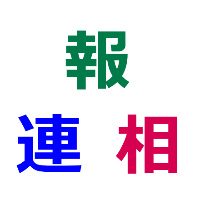
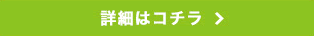
コメントを投稿するにはログインしてください。